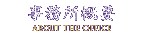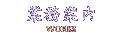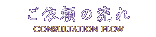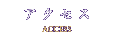平成29年7月2日、我々神奈川県弁護士会公害環境問題委員会有志は、カヌーに乗って奄美大島のマングローブの森の調査に出かけた。
筆者はマングローブとは特定の植物の名称と誤解していたのだが、そうではない。マングローブとは、熱帯、亜熱帯において、満潮時に海水が侵入する河口の湿地帯に群生する樹木群の総称である。マングローブの森に群生している植物は、そもそも陸地に生息していたが、生存競争に敗れ、陸地から海水の侵入する河口付近に生育場所を求めて移動してきたものである。
さて、調査当日、我々は川幅の広い川の本流にある発着場から出発した。出発時は、満潮であったので、川の水面は潮の満ち引きの影響がなくとても穏やかで、カヌーを漕ぐため力をこめるひつようはない。軽く漕ぐだけで、カヌーはスイスイと水面を進んでいく。
しばらく進むと、川の本流から外れ、マングローブの森の中に通じる細い水路に入っていった。
マングローブの森は、水路の間近に木々が迫っている。水路際に生育している木々の根本は水につかっている状態である、さらに潮の干満により森の中にも海水を含んだ水が入り込むようである。

マングローブの森に群生している植物は、海水の侵入する河口に育っているが、塩分を栄養として体内に取り込んでいるわけではない。体内に入った塩分は、葉から体外に排出する。塩分を排出する役割を持つ葉は、黄色がかった色をしている。黄色がかった葉を噛んでみると確かに塩っ辛い味がした。

細い水路を抜け、再び川の本流に戻る。本流を少し下流に向けて下り、再び細い水路に入っていく。この細い水路からは帰路となり、上流に向かってカヌーを漕ぐことになる。細い水路の両岸にマングローブの樹木が迫り、木々は我々の頭上を覆い、まるで樹木のトンネルの中を進むようである。

川の上流に向かって戻る帰路は、既に干潮の時間帯になっていた。引き潮の流れに反して、カヌーを漕ぐことになり、相当な労力を必要とし、漕いでもあまり前には進まない。また、水路の水深はみるみる浅くなっていく。木々を見ると根本に近い部分が水面から顔を出している。水面から顔を出している部分は、濡れていて今まで水に浸かっていたことがよくわかる。

水深の浅くなった水路を進むと、カヌーの船底が川底の接触する場所もあり、漕いで進むことは困難となった。船底を川底に擦りながら無理やりカヌーを漕ぐとカヌーを傷めてしまうそうだ。我々は、漕ぐことを諦めカヌーを降りて手で曳き、川を歩いて進むことになった。細い水路の出口までカヌーを引きながら歩いて進むと川の本流に突き当たり、カヌーを漕ぐのに十分な水深となった。ここで再びカヌーに乗り込むことになるが、発着場での乗り込みと異なり、スロープがあるわけではない。水面にぷかぷか浮かぶカヌーに簡単には乗り込めない。何度かトライしているうちに、びしょ濡れになってしまった。仕方なく浅瀬にカヌーを引き寄せて船底を川底につけて動かないようにして、ようやく乗り込むことが出来た。そしてしばらく引き潮に逆らいながら漕いで発着場に戻り、マングローブの森の調査を終えた。
出発から発着場に戻るまで1時間半を要した行程であった。